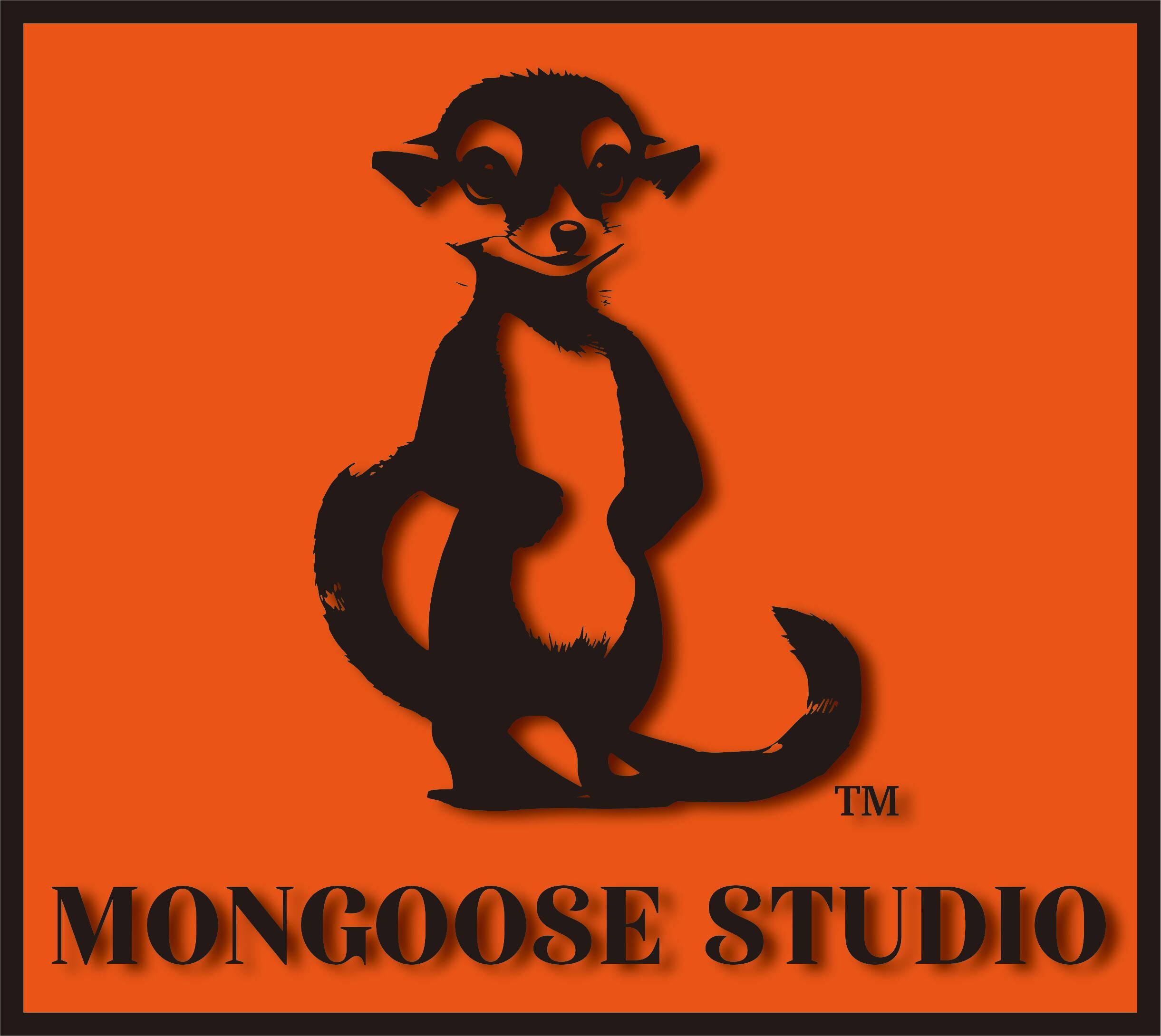MONGOOSE STUDIO は、現在準備中です。
『マングースが沖縄の生態系を乱している!』
『マングースは害獣だ!』
確かにマングースは害獣だ。
沖縄の在来種ではない。
生態系をも乱している。
では、なぜ?
在来種ではないマングースが、
沖縄の生態系を乱すことになったのか?
1910年に、渡瀬庄三郎という動物学者によって、
ガンジス川流域で捕獲されたフイリマングースが沖縄に持ち込まれました。
その目的は、サトウキビ農園に害をもたらしていたネズミの駆除と、
ハブの駆除でした。
現在沖縄にいるマングースは、
そのときに持ち込まれた、
17頭のマングースの子孫です。
害獣の天敵を導入することによって、
害獣をコントロールする方法を生物的防除といいます。
当時、マングースによる生物的防除は、
沖縄に限らず世界の他の地域でも行われました。
沖縄にマングースを導入した渡瀬庄三郎は、
生物の分布について研究し、
渡瀬線という有名な生物分布の境界を提唱した学者でした。
生物の分布について研究している学者ですら、
ほんの100年前まで、
外来の動物を自然界に導入する危険性について、
それほど理解していなかったのです。
島に生息している肉食者は、
大陸に生息している肉食者よりも種が限られていることが多いです。
そのため島では、
天敵から逃げる能力の低い、
飛べない鳥や動きの遅い爬虫類でも繁栄することができます。
そんなところに、
大陸仕込みのハンティングの名手を入れた結果は、
火を見るよりも明らかです。
なんでも食べるマングースは、
片っ端から捕まえやすい生き物を捕食して、
どんどん沖縄に広がりました。
沖縄では、
マングースが侵入した地域で顕著にヤンバルクイナが減少し、
1985年からの20年間だけで生息域は、
40%減少しました。
絶滅危惧種に指定されているハナサキガエルやオキナワキノボリトカゲ、
鳥類のホントウアカヒゲなど、
多くの分類群の希少種がマングースにより
捕食されていることが明らかになりました。
奄美大島でも、
アマミノクロウサギ、ケナガネズミなどの
希少種を捕食していることが確認されています。
ハブの数を減らすために導入したマングースですが、
結局ハブはほとんど食べることありませんでした。
それどころか、
在来の生物を捕食し、
爆発的に個体数を増やした結果、
本来の生態系に甚大な被害を与えています。
しかし、これはマングースが悪いわけではなく、
明らかに人為的ミスではないでしょうか?
しかし、マングースをコントロールすることもできない。
そう考えていたある日、 ふと思いついたのです。
『そうだ、マングースを主人公にしたブランドを作ろう!』
その売上を、沖縄の自然を保護する団体に寄付することで、
間接的ではありますが、
マングースが沖縄の自然保護に携わるという逆転の発想です。
みなさん、
決してマングースが悪いわけではありません。。
むしろ、勝手に害獣扱いされた被害者なのです。
このブランドには、
マングースの立場も尊重し、
沖縄の自然、環境も守りたい。
マングースも沖縄の自然保護を守れる。
(間接的ではあるが)
そんな想いが込められています。
このブランドの売上の一部は、
沖縄の自然保護団体に寄付されています。